国会議員や都道府県知事などの選挙では、通常は午前7時に投票を開始するのですが、その日の1番目に投票する有権者の方には大切な役目があります。
それは、組み立て前の投票箱の中身が空(から)であることの確認です。
私は中の人(投票所の責任者;投票管理者)をやっていたことがあるので少し説明しますと、組み立て前というのが重要です。
というのも、投票所の事務従事者(中の人)に悪意があった場合に、勝手に投票用紙に候補者名や政党名などを書いて、投票箱に入れることも可能だからです。
もろろん、中の人はそんなことはしませんが、可能性としてはあり得ることなので、その不正がないことを確認する必要があるのです。(公職選挙法施行令第34条で決まっています。)
公職選挙法施行令
(投票箱に何も入つていないことの確認)
第三十四条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。
その確認は、以下の人が行います。
- 投票所の責任者1名(;投票管理者と言い、通常は役所・役場の管理職が務めます。)
- 投票所の立会人2名(あらかじめ選挙管理委員会が選出)
- 一番早く投票所に来られた当日有権者1名(当日決定)
その「一番早く投票所に来られた当日有権者」は、最近「ゼロ票確認ガチ勢」とか「零票確認ガチ勢」とかネット界隈では言われていて、それを目的に早起きして、投票所に1番乗りする方もいます。(実際、毎回1番乗りの常連さんがいることもあります。)
では、何時間前に投票所に行けば、1番乗りできるかと言えば、それは何とも言えません。
私が担当していた投票所では、投票事務従事者は午前6時に現地に集合し、そこから午前7時までに最後の準備と最終確認をします。
そんな訳で集合時刻の午前6時に投票所に行くのですが、すでに投票所の入口前で「ゼロ票確認ガチ勢」の方が待っていることもあります。(というか、中の人より先に来て待っているのがほとんどです。)
ちなみに、土足用の養生シート、記載台、机や椅子などの準備は、前日の土曜日に半日かけて行います。また、投票管理者は当日は午前5時過ぎには選挙管理委員会事務局に行き、投票用紙や当日有権者のデータが収録されたUSBメモリなどを受け取って、投票所に向かいます。当然ですが、寝過ごしはできませんし、交通事故を絶対に起こさないよう、それは尋常ではないプレッシャーがありまして、目覚まし時計2個+テレビのタイマー起動など、二重三重の対策を行っても、前日は熟睡なんてとても不可能です。
さて、「ゼロ票確認ガチ勢」についてですが、いつかの選挙で担当した投票所が小学校の体育館で、学校の門が3か所あり、そのうち2か所の校門で6時前から待っている人がいて、誰が1番乗りか揉めたことがありました。
その時は話し合いで決めていただきましたが、次回以降は、前日の土曜日から各門に「1番乗りの方は正門前でお待ちください。」の案内図付きの掲示をするようにしました。
ということで、「ゼロ票確認ガチ勢」を狙う方は、事前に選挙管理委員会に電話して、投票所のどこの場所で待てばいいか確認するのが良いと思います。
さて、ラジオの時報で午前7時00分を投票を開始するのですが、投票管理者は入口で皆さんに聞こえるように以下のアナウンスします。
「ただいまから、○○選挙の投票を開始いたします。」
「公職選挙法により、1番目に投票される方には空の投票箱の確認をいただきますので、今しばらくお待ちください。」
このアナウンスをしないと、「いつまで待たせるのか。」とか「まだ中に入れないのか。」とか、お叱りをいただく源になるので、まさに予防的に行うものです。
ということで、アナウンス後に「ゼロ票確認ガチ勢」の方を投票所内にお連れして、空の投票箱の確認をしていただいて、投票箱を組み立てて南京錠で施錠、そこから午後8時までの投票がスタートします。
これは中の人だから知っていることですが、「ゼロ票確認ガチ勢」は大切な役目を担ったという名誉だけではありません。
実は投票所で作成する書類にお名前が残ります。
その書類は「投票録(とうひょうろく)」と言いますが、「投票管理者」、「投票立会人」とともに、「1番に投票した人」の氏名も記録を残します。
中の人には毎度のことで、空の投票箱は珍しいものではありませんが、空の投票箱を見てみたい方は、以下の手段がありますのでご参考まで。
- 「ゼロ票確認ガチ勢」になる。
- 「投票立会人」になる。
- 中の人(臨時事務職員(アルバイト))になる。(投票日の1か月前頃までに、選挙管理委員会事務局に投票所のアルバイトがないか聞いてみるのが良いでしょう。)
以上、選挙の投票についての裏話のご紹介でした。

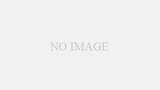
コメント