2024年7月現在、ロボアドバイザー2社と運用コストが低いインデックスファンドである「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(通称:オルカン)」で資産運用を行っている。
先日の投稿では、2024年7月のドル安円高・株安の相場によって、7月11日時点の含み益を100とすると、7月30日時点では72.5と1か月弱の期間で27.5%目減りし、金額としては数百万円の含み益が溶けたことに触れた。
一般的に投資では、損失のリスクを軽減するために「分散」が言われ、分散の手法としては「時間分散」、「投資先の分散」、「投資商品の分散」がある。
「時間分散」はドルコスト平均法で資金を積み立てすること、「投資先の分散」は複数の国の株式市場や複数企業の株式に資金を投入すること、「投資商品の分散」は株式と債券など資産クラス(株式、債券、不動産、貴金属、現預金などの投資対象となる資産の種類や分類)を分けて資金を投入することである。
ロボアドバイザーとオルカンでは、資産クラスが以下のように異なっている。
1 ウェルスナビ(ロボアドバイザー)
- 投資対象:ETF(外国株式、国内株式、外国債券、金、不動産)
- 資産配分:株式39%、債券50%、金・不動産11%(リスクレベル2の自動設定)
2 Theo(テオ)(ロボアドバイザー)
- 投資対象:ETF(外国株式、国内株式、外国債券、金・銀、不動産、その他)
- 資産配分:株式39%、債券44%、金・銀・不動産・その他17%(年齢と就業の有無で自動設定)
3 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(インデックスファンド)
- 投資対象:外国株式、国内株式
- 資産配分:株式100%、ベンチマーク:MSCI ACWI(組み入れ銘柄は約3,000銘柄)
ロボアドバイザー2社は、株式、債券、その他(金、不動産など)のETFに分散投資しており、オルカンは全世界に分散投資しているが資産クラスとしては株式のみである。
2024年7月は、ドル安円高、株安により含み益が大きく減ったが、その内訳は以下となった。
1 ウェルスナビ(ロボアドバイザー)
- 評価額の最大(7月10日):4,307,324円 → 8月1日の評価額:2,916,862円
- 評価額の差(含み損益):-1,390,462円(7月10日から-32.3%)
2 Theo(テオ)(ロボアドバイザー)
- 評価額の最大(7月11日):5,361,882円 → 8月1日の評価額:3,541,077円
- 評価額の差(含み損益):-1,820,805円(7月11日から-34.0%)
3 eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(インデックスファンド)
- 評価額の最大(7月11日):11,900,291円 → 8月1日の評価額:7,670,667円
- 評価額の差(含み損益):-4,229,624円(7月11日から-35.5%)
あらためて、含み益が大きく減ったことに唖然としたが、ロボアドバイザー2社の含み益の減少割合が、-32.3%と-34.0%であった一方、オルカンは-35.5%であった。
この下落はドル安円高による影響を含むもので、かつ運用期間もロボアドバイザー2社(26か月)とオルカン(16か月)と異なるため、この結果を単純に比較して良いかはあるものの、信託報酬率が1%のロボアドバイザー2社が、信託報酬率が0.05775%のオルカンよりも含み益の減少を抑えたということになった。
「信託報酬率」と「損失軽減の効果」について、費用対効果が高いのか/低いのか、大差ないのかは意見が分かれると思うが、ロボアドバイザーが「株式だけでなく、債券や金などにも分散投資をしている。」ことを強みとして宣伝するほどのインパクトはなかったように思う。
逆に、ほったらかし投資では、「長期」「分散」「低コスト」を原則として、オルカン一本を推しているが、それが実際に確認できたという印象を持った。

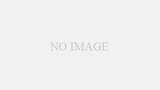
コメント