先日の投稿では、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)(通称:オルカン)」よりも信託報酬率が低い「SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)」が10月1日から販売されることに触れた。詳細は以下のリンクからご覧いただければと思う。
SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)(愛称:スマートベータ・世界高配当株式(分配重視型))
オルカンとの主な違いは、1) SBIアセット独自の基準に基づいて銘柄を選定、ポートフォリオを構築すること(ベンチマークはない。)、2) 年4回の配当があることである。
1) の「SBIアセット独自の基準」に関係するのが、愛称にある「スマートベータ」である。
インデックス指数は構成銘柄の時価総額に応じて組入れが決定されるため、時価総額が上位の大型銘柄の株価が大きく寄与するが、「スマートベータ」では財務諸表や株価の変動率などで組入銘柄/比率を決めるため、インデックス運用では投資対象とならない小型株やバリュー株を組み入れ、中長期的に市場平均を上回る成績を目指すという。
「ほったらかし投資術」の著者である山崎元氏が繰り返し発信していた「平均投資有利の原則(;相対的な運用競争にあってはアクティブ運用の平均を持ってじっとしているのが有利である。)」からは離れる部分はあるが、それも許容範囲内と思われる。
また、信託報酬率を抑えることができる理由のひとつとして、インデックスの使用料がないことがあると思われる。
例えばオルカンの場合はベンチマークであるMSCI ACWIのインデックス使用料が運用経費となるため、信託報酬率の引き下げにも限界があり、現行の0.05775%はその限界に近いものと考えられる。一方で、スマートベータであれば、インデックスの使用料は発生せず、この点が低コストに大きく寄与していると思われる。
「アクティブファンドは運用コストが高い。」というこれまでの常識は、今後は変わっていく可能性も考えられ、「ほったらかし投資術」の最適解もオルカン一本だけでなく、時々刻々と変わっていくことも頭に入れて、資産運用を行っていく必要がありそうだ。
※ 私はSMBC日興証券のダイレクトコースしか証券口座を開設していないため、現状、SBI証券1社での販売となるこのファンドを購入することはできない。苦笑

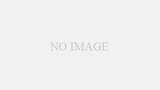
コメント