はじめに
新年を迎えると確定申告の準備に入りますが、証券会社やロボアドバイザーの分配金・譲渡益を確定申告(所得税・住民税の還付申告)するか否か、頭を悩ませます。
証券会社やロボアドバイザーの特定口座(源泉徴収あり)では、ETF(上場投資信託)や投資信託を運用した場合に得られた分配金や譲渡益については、20.315%の税金(所得税・住民税)が源泉徴収されています。
源泉徴収された税金は、証券会社やロボアドバイザーが納税の手続きをするので、基本的には個人投資家は放置していても問題はありません。
ただし、私のように給与所得がない場合は、確定申告すると源泉徴収された所得税・住民税が還付され、税負担を軽減できることがあります。
分配金や譲渡益の課税方法
分配金や譲渡益の課税方法には、(1)総合課税、(2)申告分離課税、(3)源泉徴収による納税(確定申告不要制度)の3種類があります。
1.総合課税(確定申告が必要)
- 対象の所得すべてを合算して所得税を計算する。
- 所得が多いほど税率が上がる累進課税方式を採用している。
- 上場株式等の配当金(配当所得)は、総合課税/申告分離課税の選択ができる。
2.申告分離課税(確定申告が必要)
- 他の所得と分離して所得税を計算する。
- 所得の種類ごとに税率が異なる。
- 上場株式等の配当金(配当所得)は、総合課税/申告分離課税の選択ができる。
- 配当所得では上場株式等の譲渡損と配当益を「損益通算」できる。
3.源泉徴収による納税(確定申告不要制度)
- 他の所得と分離して所得税を計算し、証券会社等が税金を徴収し納税者に代わって納める。
- 配当所得は、上場株式等の譲渡損と配当益を「損益通算」できる。
それぞれの課税方法 ー 経済的なメリット/デメリット
確定申告をしない3.源泉徴収による納税(確定申告不要制度)の場合、所得税・住民税の節税はできません。ただし、「配当所得・譲渡所得」が「合計所得金額」に算入されないため、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料が増えることはありません。
確定申告をする1.総合課税、2.申告分離課税の場合、所得税・住民税の節税ができます。しかし、「配当所得・譲渡所得」が「合計所得金額」に算入されるため、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料が増えることになります。
複雑なので、以下の表でまとめました。
| 納税の方法 | 確定申告 | 所得税・住民税の還付 | 国民健康保険料など |
| 1.総合課税 | 必要 | 還付あり(節税)↓ | 3より増える↑ |
| 2.申告分離課税 | 必要 | 還付あり(節税)↓ | 3より増える↑ |
| 3.源泉徴収による納税(確定申告不要制度) | 不要 | 還付なし | ー |
つまり「還付される所得税・住民税の金額」と「国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料の増額」を総合的に見極める必要があります。
税金の還付額と保険料の増額を見極める手順は?
見極めの手順は以下となる。
- 証券会社や銀行等から交付される「特定口座年間取引報告書」を入手する。(通常は翌年1月に交付される。)
- 国税庁確定申告書等作成コーナーで「特定口座年間取引報告書」の情報を入力し、所得税の還付金額を算出する。(配当所得は申告分離課税項目で算出する。)→①
- お住まいの市町村の「住民税試算システム」などで「特定口座年間取引報告書」の情報を入力し、住民税の還付金額を算出する。(配当所得は申告分離課税項目で算出する。)→②
- お住まいの市町村に問い合わせし、「特定口座年間取引報告書」の情報を伝え、「国民健康保険料」を調べる。(所得割、均等割、平等割が分かれば自分でも計算できる。)→③
- あわせて、確定申告しない場合の「国民健康保険料」を調べる。→④
確定申告する/しないの判断は?
- 所得税・住民税の還付額(①+②) > 国民健康保険料など保険料増額(③-④) → 還付申告する方が得になる。
- 所得税・住民税の還付額(①+②) < 国民健康保険料など保険料増額(③-④) → 還付申告しない方が得になる。
確定申告して約52,000円の節税に
例えば、昨年の私の場合、①:\100,345-、②:\30,058-、③:\102,092-、④\23,850-となり、
所得税・住民税の還付額(①+②) > 国民健康保険料など保険料増額(③-④)であったため、確定申告する方が約52,000円の節税となる結果でした。
3月の確定申告の期限までに時間は十分にありますので、よく試算して還付申告するか/しないか、判断して欲しいと思います。

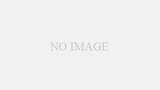
コメント