ロボアドバイザー投資の基本は「長期・分散・積立」。
これはウェルスナビが掲げる投資方針でもあり、初心者でも実践しやすい王道のスタイルです。
2022年4月に、私はウェルスナビとTheo(テオ)の2社でロボアドバイザー投資を開始しました。
月額50万円を積み立て設定し、実際の運用結果を比較しています。
ウェルスナビが提唱する「長期・分散・積立」の投資とは
ウェルスナビでは、年齢・就業状況(現役/退職)・リスク許容度を入力すると、自動的に資産配分が決まり、最適なポートフォリオ(金融商品の組み合わせ)が作成されます。
資産は「株式」「債券」「金」「不動産」にバランスよく分散されます。
私の場合はリスク許容度を2(5段階のうち低い方から2番目)に設定したところ、
- 株式39%
- 債券50%
- 金・不動産11%
という構成になりました。
Theo(テオ)は年齢と就業状況で自動的に資産配分が決まり、
- 株式39%
- 債券44%
- 金・銀・不動産・その他17%
という結果でした。
ウェルスナビとTheo(テオ)のETF構成の違い
入金すると、設定された資産配分に従って海外ETF(上場投資信託)が自動購入されます。
ウェルスナビで購入されるETF(ティッカーコード)は以下の7種類です。
- 米国株:VTI
- 日欧株:VEA
- 新興国株:VWO
- 債券:AGG・TIP
- 金:GLD・IAU
- 不動産:IYR
一方で、Theo(テオ)は40種類以上のETFに分散投資しています。
どちらも1〜6か月に一度、ETFから配当が支払われ、税引き後に自動再投資されます。
少額ながら、資産が増えていく実感があります。
実際の運用データ(2022年)
ウェルスナビの運用実績(円ベース・通算)
2022年4月にスタート。当時のドル円は1ドル=125円前後。
コロナショック明けの回復期にあたる時期でした。
| 月 | 成績(%) |
|---|---|
| 5月 | -0.81 |
| 6月 | +0.46 |
| 7月 | -0.19 |
| 8月 | +0.17 |
| 9月 | +2.00 |
| 10月 | -1.75 |
| 11月 | +2.92 |
| 12月 | +0.21 |
Theo(テオ)の運用実績(円ベース・通算)
| 月 | 成績(%) |
|---|---|
| 5月 | -1.34 |
| 6月 | +1.00 |
| 7月 | -0.13 |
| 8月 | +2.35 |
| 9月 | +2.72 |
| 10月 | -1.59 |
| 11月 | +4.08 |
| 12月 | +0.24 |
全体として、2社の運用実績はほぼ同等でした。
運用して感じたメリット・デメリット
✅ 良かった点
- 完全自動で分散投資ができる
- 配当が再投資され、複利効果を実感できる
- 世界的に分散されている安心感がある
⚠️ 気になった点
- 相場が下がると収支がすぐマイナスになる
- 運用報酬(手数料)が常に引かれる
- 想定より短期的な変動が大きい
特に、マイナス収支でも手数料が引かれる点は心理的にストレスを感じました。
まとめ|地味でも続けることが大切
ウェルスナビもTheo(テオ)も、2022年は一進一退の結果でしたが、「長期・分散・積立」の考え方を守って続けることが大切だと感じました。
投資は短期の上下よりも時間を味方につけることが重要です。
地道に積み立てを継続し、今後も2社の運用実績を追っていきます。

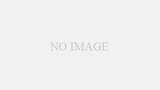
コメント