投資初心者の中で話題の「ほったらかし投資術」。
実はこの本、ロボアドバイザーとは違う“本当の意味でのほったらかし投資”を提案しています。
本記事では、実際にロボアドバイザーで資産運用してきた筆者の体験をもとに、
『ほったらかし投資術』の内容とロボアドとの違い、そして最適な運用方法について解説します。
■ ロボアドバイザーでの資産運用実績
投資知識ゼロの状態からロボアドバイザーを利用して資産運用を開始。
運用内容は以下の通りです。
- 金融商品:海外ETF(株式、債券、金・銀、不動産)
- 資産配分:株式39%、債券50%、その他(金・不動産)11%
- 運用手数料:評価額の1.1%(年率・税込)
- 実績利回り:年10%(2022年4月〜2024年6月)
ただし、この10%はコロナ後の特需による一時的な数値であり、実際には年5%程度が現実的な水準と考えられます。
■ 「ほったらかし投資術」とは何か?
2023年2月、筆者は資産運用を学ぶ中でる【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術(朝日新書)に出会いました。
Amazonレビューでは“投資初心者のバイブル”と評されるほど人気の高い書籍です。
本書では、「長期・分散・低コスト」を資産運用の3原則として掲げ、個人投資家が無理なく実践できる「インデックスファンド投資」を推奨しています。
■ 推奨される資産運用の考え方
著者が推奨する基本方針は以下の通りです。
- 生活費の3〜6か月分を現金で確保
- 残りをリスク資産(全世界株式インデックスファンド)で運用
- 無リスク資産を保有するならば、個人向け国債または預貯金(1,000万円以内)
このシンプルな戦略により、プロの投資家に劣らない成果を低コストで実現できると述べられています。
■ ロボアドバイザーが推奨されない理由
「ほったらかし投資術」では、ロボアドバイザーを推奨していません。
理由は明確で、手数料が高いからです。
- ロボアドバイザー:年1.1%
- インデックスファンド:年0.1〜0.25%程度
100万円を運用した場合、手数料は1年間で約1万円の差。
長期運用ではこの差が複利で拡大し、資産形成に大きな影響を与えます。
■ 結論:インデックスファンド運用が最適解
筆者自身、ロボアドでの成果に満足しつつも、『ほったらかし投資術』を読んだことで、より合理的な方法に気づきました。
今後は、「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を中心とした低コストなインデックスファンド運用に切り替えていく方針です。
✅ まとめ
- 「ほったらかし投資術」は“長期・分散・低コスト”が原則
- ロボアドバイザーは便利だが手数料が高い
- インデックスファンドなら同等の成果をより低コストで実現可能

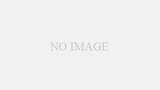
コメント