はじめに
私は、2022年3月末に会社を退職し、知識ゼロから資産運用を始めました。
最初は本やネットの情報を浴びるように吸収しましたが、情報量が増えるほどに “もっと儲かる” “裏技的手段” といった誘惑もまた増えてきます。
本稿では、情報に踊らされず、地に足をつけた運用を続けるための心得を、自分の体験を交えて共有します。
1.投資スタートの背景
退職時点で私は、社内預金という元本保証の制度を利用していました(年利約1.56%)。しかし退職によって解約、利息は途絶え、すべての資金が手元に戻ってきました。
その時点で資産運用の知識はゼロで、あまり考えずに手近にロボアドバイザー2社での積立を始め、その後2023年2月に【全面改訂 第3版】ほったらかし投資術(朝日新書)を読書ノートを取りながら読み、「長期・分散・低コスト」という投資の基本を学びました。
また、eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー=通称オルカン)の特徴(分散、構成銘柄の自動入れ替え、低コスト)を理解し、積立も並行して始め、現在に至ります。
2.情報量の増加とその影響
運用を始めると、株式や投信、ロボアド、仮想通貨、レバレッジ商品など、ありとあらゆる投資情報が飛び込んできます。
ただし、ネット上には炎上目的や煽動目的の投稿、ポジショントーク、自利的な主張も多数混じっており、 善悪・真偽を見極める能力(金融リテラシー) が不可欠になります。
3.“悪魔の囁き”の典型例
特に目を引く誘惑例として、以下が挙げられます:
- 個別株やFXなら短期で大きく儲かる
- 「iFreeNEXT FANG+インデックス」や「レバレッジ型投信」が高リターンをもたらす
- 高配当投資信託で“定期収入”を得よう
- 分配金型投信は安定した収入源
これらは耳障りの良い言葉ですが、運用コスト、税制、価格変動リスクなどの裏側には、必ずデメリットが存在します。
4.山崎元氏の教えと “最適位置” の保持
著書『ほったらかし投資術』の著者・山崎元氏は、「相手の平均を持ってじっとしている」が最適解であると述べます。
つまり、情報の誘惑に惑わされてポジションを変えることは、「最適な状態」から離れる行為とも言えます。
5.情報と欲のスパイラルとその予防策
情報量 ↗ → 情報の善悪/真偽の判断ミス ↗ → 欲を出した極端な運用 → 成功体験による過信、というスパイラルが生まれやすい。
これを防ぐには、以下の対策が有効です:
- 日々の情報をすべて追わない(フィルタリングをかける)
- 骨格の運用方針(例えば、オルカン+ロボアド併用など)を決めておき、ぶれないようにする
- 説得力のある根拠を求め、短期の煽りやキャッチコピーに飛びつかない
- 定期チェックはするが、頻繁なポジション変更は避ける
6.現時点での私の到達点
確かに、成績的には他の戦略に劣る局面があるかもしれません。しかし現時点では オルカン+ほったらかし運用 が、雑音に惑わされずに運用を続ける上で最も現実的な選択肢だと考えています。
まとめ
運用情報が増えることは、知識の拡充にはつながる反面、“誘惑” をも強めます。
だからこそ、情報の取捨選択力を鍛え、堅実な運用方針を持って、揺るがない心構えで投資を続けることが大切です。
最も重要なのは、長期・分散・低コストという基本を守る姿勢を貫くことです。

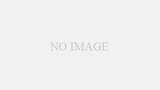
コメント